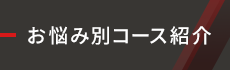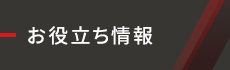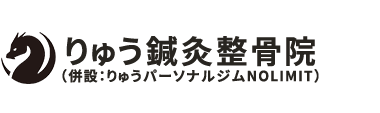ひざに水がたまる原因とは?
概要

「膝に水がたまる」とは、医学的には「膝関節内の滑膜(関節の内側にある膜)が炎症を起こし、関節液(滑液)が過剰に分泌・貯留している」状態を指します。
その結果、ひざが腫れたり違和感や痛みが生じ、日常生活にも大きな支障をきたします。
今回は、初期症状から詳しい原因、治療後の注意点まで医学的根拠をベースに徹底解説します。
ひざに水がたまる原因とは?
①膝に水がたまる初期症状を知ろう

ひざに水(関節液)がたまる初期には、次のような症状が現れます。
1)膝の腫れや膨らみ
・膝蓋骨(お皿)周囲が丸く膨らみ、押すと柔らかくプニプニした感触。
2)重だるさ・違和感
・膝を曲げたり伸ばしたりすると重く感じ、歩き始めや階段昇降がつらい。
3)曲げ伸ばしの制限
・正座やしゃがむ動作が困難になる、屈伸がしづらい。
4)熱感・赤み
・特に炎症が強いと患部に熱を持ち、皮膚が赤くなってくることもあります。
※初期段階では「腫れているだけ」と感じる人も多いですが、その裏で関節組織の炎症が進行しています。症状が進むと圧迫感・痛みも強くなります
ひざに水がたまる原因とは?
②水がたまる原因とそのメカニズム

ひざ関節には普段から微量の「関節液(滑液)=水」が存在しています。(以降、水と表現します)
水は、軟骨の保護や関節の動きを滑らかにする働き、栄養供給の役割を果たしています。
しかし、炎症が起こると滑膜の分泌機能が過剰になり、ひざ内の許容量を超えて、水が分泌するため、水が溜まる状態になります。
以上が「膝に水がたまる」状態のメカニズムです。
では、なぜ炎症が起きるのかを説明します。
1)変形性膝関節症
・加齢や体重、ひざへの負担がかかることで軟骨がすり減り、摩耗した軟骨の破片が滑膜を刺激して炎症が起きます。
2)半月板損傷・靭帯損傷
・外傷、スポーツでひざ内部の損傷や摩耗が起こり、関節内にて出血や滑膜の炎症が発生します。
3)関節リウマチ
・免疫異常によって、自分自身の滑膜を攻撃することで慢性的な炎症が起きますが、これはひざ以外の関節にも症状が出ることが多いです。朝方のこわばりや左右対称の腫れが特徴的です。
4)痛風・偽痛風
・尿酸類やピロリン酸カルシウムなどの結晶が沈着し、関節内に急性的な炎症が発生します。
5)感染性関節炎
・細菌などによって急性炎症が発生します。高熱や激烈な痛み伴い緊急治療が必要。
6)その他(筋力不足・過度な運動・加齢)
・負荷や老化、過剰な摩耗で滑膜の炎症が起きます。筋力低下もリスク要因となります。
ひざ関節が日常の繰り返し運動や外傷、免疫異常などをきっかけに、「滑膜」が炎症を起こし、水の過剰分泌が起きる→吸収が追いつかず貯留する→膝が腫れて痛みや可動域(動き)制限となります。
ひざに水がたまる原因とは?
③膝の水を抜いた後の注意点

膝の水を抜くこと(関節穿刺)は、症状緩和のために行われるイメージを持たれますが、根本的な治療ではありません。その後に重要なのは原因を根本的に改善することです。
【原因疾患の継続治療】
変形性膝関節症やリウマチ等の疾患の場合、治療(リハビリ・薬物療法・体重管理など)で炎症の再発を防がなければいけません。
※整骨院や整体院、トレーニングジムでできる根本的アプローチは、
1)負担のかかって動きの悪い関節や筋肉を緩めること
2)身体の使い方を正す運動療法を行うこと
3)筋力を向上させて関節の負担を減らすこと
メインはこの3つだと考えています。
病院や整形外科でしかできないこと、整骨院や整体でできることを理解して適切な処置を受けるようにしましょう。
また、「水を抜くとクセになる」というのは医学的には「誤解」です。
水が頻繁に貯留するということは、炎症や疾患のコントロールが不十分な証拠です。
水抜きだけに頼るのではなく、先ほどお伝えした根本治療が重要です。

〒612-0029 京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目107 宮田ビル
1階:りゅう鍼灸整骨院 / パーソナルジムNOLIMIT(リハビリ・姿勢・ダイエット)
2階:アスリート専門パーソナルジムIMPRESS GYM(リハビリ・筋力向上・パフォーマンス向上)
TEL:075-644-4713
※全スタッフがお客様対応中の場合、お電話に出ることができません。
「当施設へのご質問」や「整体/トレーニングのご予約」は、公式LINEのご利用をお願いいたします。
【LINEアカウント】

【Instagram】

※この記事で使用しているイラスト画像は、全て著作権フリー画像です。